IT-BCPとは? 策定する際の5つのポイント
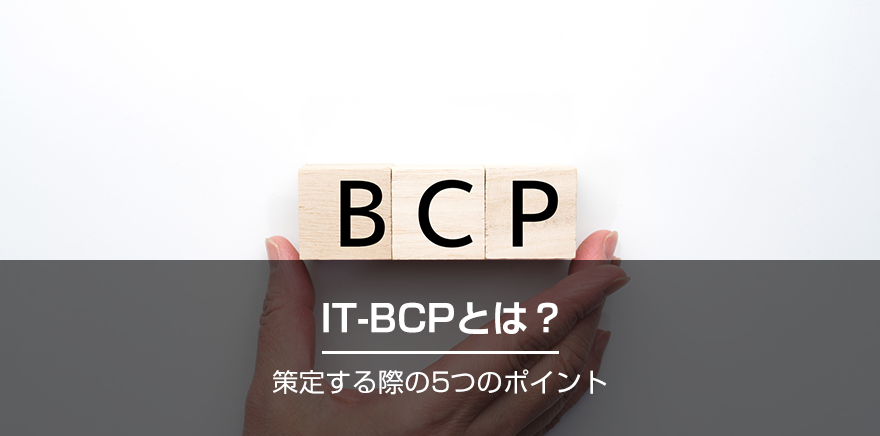
自然災害やサイバー攻撃などの被害に遭うと、業務が中断したり機密情報が漏洩したりと、事業運営に深刻な影響を与えることがあります。そのため、企業は事前にIT-BCP(IT事業継続計画)を策定し、万が一に備えることが重要です。しかし、IT-BCPをどう策定すればよいか悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、IT-BCPとは何か解説しつつ、具体例や策定のポイントを紹介します。法的リスクの軽減や顧客との関係性維持のためにも、ぜひ参考にしてください。
IT-BCPとは

IT-BCPはBCPの一部であり、それぞれ対象とするリスクや焦点が異なります。ここでは、IT-BCPとは何か、BCPとの違いを解説します。
BCP:事業継続計画のこと
BCP(事業継続計画)とは、企業が災害や事故、サイバー攻撃、パンデミックなどの緊急事態に直面した際に、重要な業務を継続し、できるだけ早期に復旧させるための計画を指します。目的は、被害を最小限に抑え、事業の中核となる業務を維持し、顧客や取引先への影響を減らすことです。
この計画には、リスクの評価、対応策の策定、復旧手順の確立、代替手段の準備、従業員の役割分担、緊急時のコミュニケーション方法などが含まれます。
企業は万が一の事態に備えるため、平時から訓練やテストをすることが重要です。特に、グローバル化やデジタル化が進む現代では、自然災害だけでなく、サイバー攻撃への対策も欠かせません。
IT-BCP:ITシステムの事業継続計画のこと
IT-BCPは、BCP(事業継続計画)の一部であり、災害やサイバー攻撃などの緊急事態が発生しても、ビジネスに必要不可欠なITシステムを継続的に運用できるように策定する計画のことです。
現代の企業活動はITに大きく依存しており、システムの停止は業務の中断や顧客対応の遅れを引き起こし、売上の損失や社会的信用の低下につながる可能性があります。そのため、IT-BCPの策定は、事業の停止リスクを抑え、企業の安定した運営を支えるために重要な要素といえます。
対策が必要なのは、クラウドサービスや取引先のシステムと連携する「社外システム」と、社内の基幹業務を支えるサーバーやネットワーク環境といった「社内システム」です。これらのシステムが停止しないよう、バックアップの確保や代替手段の準備、即時復旧可能な体制を整えることが求められます。
IT-BCPの主な具体例

ここでは、IT-BCPの主な具体例を紹介します。
データの保管・バックアップ
企業が扱う顧客データや機密データなど、事業運営に不可欠な情報が災害やサイバー攻撃の影響を受けると、業務継続が困難になります。そのため、定期的にバックアップをして、データを安全に保管することが重要です。
バックアップデータは、1か所に保存するのではなく、複数の場所に分散して管理することが推奨されます。例えば、自社のサーバーだけでなく、クラウドストレージや外部のデータセンターなどにも保管することで、特定の拠点が被害を受けても復旧できる体制を整えられます。
代替システムの活用
システムの障害によって業務が完全に停止してしまうと、取引先や顧客への影響が大きくなり、事業継続が困難になります。そのため、万が一の事態に備えて、迅速に切り替え可能な代替システムを用意しておくことが大切です。
具体的には、サーバーやネットワーク機器を多重構成にすることで、片方がダウンした場合でも、もう一方を稼働させることが可能です。
リモートワークの導入
自然災害が発生すると、交通機関の麻痺や安全確保のために、従業員がオフィスに出社できないケースが考えられます。そのような状況でも業務を継続できるよう、あらかじめリモートワークの環境を整備しておくことが重要です。
具体的には、社内ネットワークやクラウドサービスに安全にアクセスできる仕組みを構築し、従業員が自宅やほかの安全な場所から業務を継続できるようにします。また、リモートワークの環境を整えておくことで、平常時から柔軟な働き方を実現できるというメリットもあります。
緊急事態発生時における連絡体制の構築
緊急事態が発生した際、迅速かつ正確に連絡を取り合える体制を整えておくことは、IT資産の消失や情報漏洩のリスクを最小限に抑えるために重要です。特に、サイバー攻撃や災害によって通常の通信手段が使えなくなった場合でも、確実に情報共有ができる仕組みを準備しておく必要があります。
具体的には、全従業員へ一斉に連絡を送信できるシステムや、安否確認アンケートを配信できるツールを導入し、従業員の状況をすばやく把握できるようにします。また、「誰が指揮を執るのか」「どの連絡手段を優先するのか」といった指揮系統や連絡ルールを事前に決めておくことで、混乱を防ぎ、スムーズな対応が可能です。
CSIRTの設置
CSIRT(シーサート:Computer Security Incident Response Team)とは、インシデント(予期せぬ問題や事故)が発生した際に対応する専門チームのことです。サイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティインシデントに迅速かつ適切に対処するために設置します。
CSIRTを設置すれば、万が一攻撃を受けた際に速やかに被害状況を把握し、システムの復旧や影響の最小化を図ることが可能です。さらに、セキュリティリスクを事前に評価し、脆弱性の対策を講じることで、被害に遭うリスクを軽減できます。定期的なセキュリティ監視や訓練により、企業全体のセキュリティ意識を高め、より強固なIT-BCP体制が構築できるでしょう。
IT-BCPを策定する際の5つのポイント

IT-BCPの策定をスムーズに進めるためにも、以下で紹介する5つのポイントを押さえておきましょう。
ポイント① ガイドラインを参照する
経済産業省や内閣府防災担当など、国の各機関が発行しているIT-BCPに関するガイドラインには、緊急時の対応手順や実施計画、教育・訓練の必要性などが詳細に記載されています。ガイドラインを参照することで、IT-BCP策定に必要な要素や手順が明確になり、自社の状況に合わせた適切な対策を講じることが可能です。
| 経済産業省 |
|
|---|---|
| サイバーセキュリティ戦略本部 | 重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全基準等策定指針 |
| 内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター | 政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン |
| 内閣府 防災担当 | 事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応 |
※出典:経済産業省「サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver 3.0」
※出典:経済産業省「IT サービス継続ガイドライン」
※出典:サイバーセキュリティ戦略本部「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る 安全基準等策定指針 (第5版)」
※出典:内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター「政府機関等における 情報システム運用継続計画 ガイドライン ~(第 3 版)~」
※出典:内閣府 防災担当「事業継続ガイドライン」
ポイント② IT-BCPの重要性を社内に周知する
IT-BCPは企業全体で取り組むべき課題であるため、社内でその重要性をしっかりと認識し、全従業員に周知することが大切です。まずは、IT-BCPに対応する部署やチームを編成し、緊急時に即時対応できる体制を整えましょう。さらに、対応マニュアルを作成し、状況別の対応方法を明確にしておくことも重要です。
そして全従業員にマニュアルを配布し、定期的に訓練を実施して、実際の緊急事態でもスムーズに対応できるようにしましょう。
ポイント③ 経営層の理解を得る
IT-BCPは企業全体に影響を与えるため、予算措置やリソースの割り当てを決定する経営層の判断が欠かせません。まずはIT-BCPの重要性を経営層にしっかりと説明し、リスクが現実化した場合の影響や、適切な対応策を講じる必要性を説きましょう。
その上で、経営層にも積極的にIT-BCPの策定や実行に参加してもらい、企業全体として一丸となって取り組む体制を整えることが重要です。
ポイント④ 適切な予算計画を立てる
IT-BCPを策定して実施するには、様々なコストが発生します。例えば、バックアップシステムの導入、代替システムの準備、リモートワーク環境の整備、従業員への教育・訓練など、必要な対策には相応の予算が必要です。そのため、IT-BCPを成功させるには、慎重な予算計画の立案が不可欠です。
まず、IT-BCPにおいてどのシステムやサービスが最も重要であるか、自社にとっての優先順位を明確にしましょう。そして予算を適切に分配し、限られた資源を効果的に活用してみてください。
ポイント⑤ IT資産を分散管理する
企業がもつIT資産を1か所に集約すると、災害やサイバー攻撃などの被害に遭った際に、すべてのIT資産が消失したり窃取されたりするリスクがあります。
事業の継続性を確保するためにも、「クラウドサービスを活用する」「地理的に分散した場所に配置する」など、IT資産を複数の場所で分散して管理することが必要です。
まとめ
IT-BCP(情報技術事業継続計画)は、企業が災害やサイバー攻撃などの緊急事態に直面した際に、重要なITシステムやデータを守り、業務を継続できる体制を整えるための計画です。IT-BCPの具体例としては、データの保管・バックアップ、代替システムの活用、CSIRTの設置などがあげられます。
また、IT-BCP対策には、リモートアクセスサービスの「RemoteOperator Helpdesk」の活用もお勧めです。RemoteOperator Helpdeskを活用すれば、外出先や自宅から社内PCを操作したり、システムやサーバーをリモートでメンテナンスしたりできます。
無料トライアルもあるので、リモートワークの導入を検討している場合は、ぜひ試してみてください。
