遠隔臨場とは? 推進されている背景やメリット、実施事例を紹介
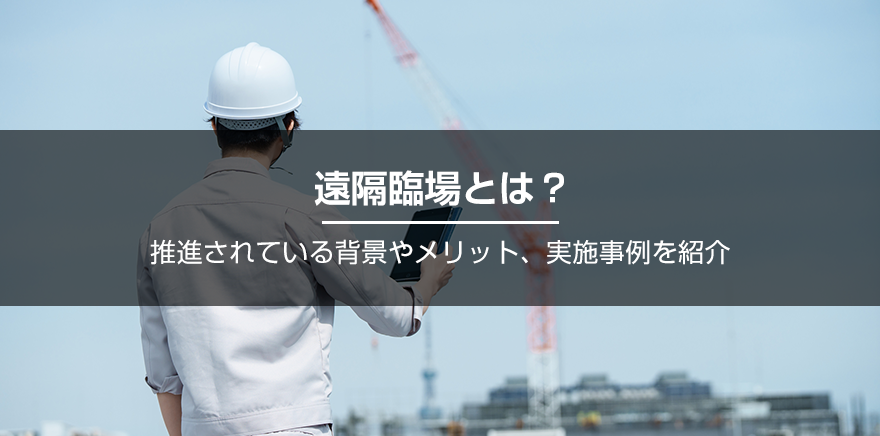
遠隔臨場は、人手不足の解消や業務負担の軽減などを目的に、IT機器を活用して遠隔地から臨場確認を行う手法です。国土交通省が令和4年度に本格導入したことで普及が進んでいます。
今回は、遠隔臨場の概要や背景をはじめ、遠隔臨場のメリット・デメリットや遠隔臨場の実施事例について解説します。
遠隔臨場とは?

遠隔臨場とは、発注者側の監督職員が工事現場に出向くことなく、遠隔地からリモートで臨場確認を実施することです。国は、遠隔臨場を以下のように定義しています。
「遠隔臨場とは、Web会議システムをはじめとする通信機器を使用して、ウェアラブルカメラなどの機材で録画した映像と音声により、材料確認や段階確認、立会を行うものである」
※出典:国土交通省「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領」
具体的には、どのように遠隔臨場が行われているのでしょうか。まずは、遠隔臨場の仕組みと必要な道具をみていきましょう。
遠隔臨場の仕組み
遠隔臨場は、撮影機材と通信機材を連携させることにより、遠隔地にいながら現場との間で、映像や音声の双方向のやり取りを可能にします。離れた場所にいる監督職員は、現場の作業員が撮影した施工現場の映像や音声を画面上で確認できます。
遠隔臨場が適用されるのは、以下の確認項目です。
| 段階確認 | 各施工段階において、出来形や品質などが設計どおりか確認する |
|---|---|
| 材料確認 | 仕様書に基づき、材料の品質や規格などを検査する |
| 立会 | 契約図書に記された項目について内容を確認する |
遠隔臨場に必要な道具
遠隔臨場には、以下の道具が使用されます。
撮影機材
| ウェアラブルカメラ | 身体やヘルメットに装着する小型カメラ。ハンズフリーで撮影できるため、安全かつ効率的に作業を進められる |
|---|---|
| 360度カメラ | カメラを中心に360度全方位を撮影できるカメラ。臨場感のある映像を撮影できるほか、撮影漏れや見逃しを防げる |
| ネットワークカメラ | インターネットに接続できるコンピューター内蔵のカメラ。一般的にLANケーブルに直接接続して利用されることが多い |
| ドローン | 遠隔操作や自動操縦で飛行する小型の無人航空機。山奥や広範囲の遠隔臨場などに用いられる |
通信機材
| Web会議システム | インターネットを介して映像や音声を共有することにより、場所を選ばずに双方向のコミュニケーションができるツール |
|---|---|
| テレビ電話 | 電話回線を使って、映像と音声を同時にやり取りできる電話システム |
以上に加え、スマートフォンやタブレット、メガネ型のウェアラブルデバイスであるスマートグラス、位置情報や振動などのデータを集めるセンサーなども使用されています。
なお、機材によって画質や機能、操作性、サポートやセキュリティ体制などは様々です。そのため、確認項目を考慮した上で工事現場の環境に適した機材を選ぶことが求められます。
遠隔臨場が推進されている背景

建設業界で遠隔臨場の普及が進んでいる理由として、以下のような社会的背景があります。
建設現場でICTの活用が推進されているため
遠隔臨場の導入は、国主導のICT推進を背景に加速しています。建設業界におけるICT化は、人材不足の解消や現場の負担軽減を目的に、情報通信技術を用いて生産性向上や魅力ある建設現場の創出を目指す試みです。遠隔臨場はその施策として期待されています。
2025年現在、国をあげて進められている建設業界のICT化プロジェクトは、国土交通省の「i-Construction」、内閣府の「BRIDGE(ブリッジ)」の2つです。以下で詳しくみていきましょう。
i-Constructionとは
測量や設計、施工、検査など、建設現場のすべてのプロセスにICT技術を導入して、生産性向上やインフラ分野の業務革新などを目指す施策です。建設現場の省人化対策である施工管理のオートメーション化の取り組みとして、遠隔臨場が推進されています。
BRIDGEとは
「BRIDGE」と呼ばれる「官民研究開発投資拡大プログラム」は、600兆円経済の実現に向けて、官民の研究開発投資の誘発を目的に立ち上げられた制度です。
「革新的建設・インフラ維持管理技術/革新的防災・減災技術」の領域において、建設分野の先進的な試行への支援が行われています。
また、BRIDGEの予算を活用した「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」でも、遠隔臨場の試行が選定されています。
コロナ禍でビジネス様式が変化したため
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、社会全体で働き方やビジネス様式が大きく変化しました。Web会議やクラウド活用などの推進もその一例です。
遠隔臨場は、以上のようなICT技術を活用したツールに支えられています。コロナ禍で急速にICTツールが普及したことは、建設業界への遠隔臨場の導入を後押ししました。
遠隔臨場を実施できれば、監督職員が現場に赴く回数を削減できるだけでなく、現場までの移動時間をカットでき、確認作業の大幅な効率化が可能となります。
また、感染症予防の観点からも遠隔臨場は効果的です。現場への人の出入りを少なくできれば、不特定多数の方同士が対面で接触する機会が減り、感染症のまん延予防につながります。
遠隔臨場のメリット・デメリット

遠隔臨場には、業務効率化や安全上のメリットがある一方で、コスト面や運用面でのデメリットもあります。以下では、メリット・デメリットそれぞれについて解説します。
遠隔臨場のメリット
遠隔臨場では、監督職員の移動が発生しません。臨場作業の工数が大幅に削減される分、確認により多くの時間と労力をかけられることから、ミスや異常の見逃しを防げる可能性が高まります。空き時間を捻出できれば、監督職員が担当できる現場の数を増やせる点もメリットです。
また、現場に遠隔操作できるカメラを設置しておくことで、災害時や危険箇所へ立ち入る際にも安全性を確保できます。
そのほか、離れた場所にいる人材同士が双方向のコミュニケーションを取れる遠隔臨場は、格好の教育の場となります。
若手人材にとっては、熟練の技術者の意見やアドバイスを聞けたり、遠隔で指導を受けたりする良い機会となるからです。過去の臨場映像は人材育成の教材としても活用されています。
遠隔臨場の回数を重ねることで若手人材の技術力が向上すれば、建築業界全体の課題となっている人材不足の解消にもつながります。
遠隔臨場のデメリット
コスト面からみると、遠隔臨場の実施には、各種機材をそろえるための初期投資のほか、システム利用料や保守管理費用などのランニングコストも発生します。現場によっては高性能な機器が必要な場合もあり、費用がかさむ可能性もあります。
そのほか、運用面では、新しいIT機器に不慣れなことから起こる人為的なミスや作業の滞りなども、遠隔臨場の導入に伴うリスクです。
また、山間やトンネルなどで課題となるのが通信環境です。遠隔臨場を行う際は、各現場の状況を考慮した上で、安定した通信環境を確保するプロセスが欠かせません。
遠隔臨場の実施事例
続いて、実際の工事で実施されている遠隔臨場の事例を紹介します。
事例① 東北地整 奈曽川橋下部工工事
国土交通省東北地方整備局が監督した橋下部工工事の事例です。橋台コンクリートを打破する際の施工状況の確認に、Webカメラを活用して遠隔臨場を実施しました。確認項目は、コンクリートの品質確認をはじめ、運搬状況や打設順序、天候です。
確認作業を容易にするための工夫として、打設箇所全体を確認できるように、定点監視カメラを3台設置したことがあります。その結果、監督職員は画面上において現場の全体把握が可能となりました。
遠隔臨場の導入により、スケジュール調整が円滑化して立合計画の幅が広がったという現場の声があるほか、監督行為の負担軽減につながったという発注側からも評価されています。
※出典:国土交通省「建設現場における遠隔臨場 取組事例集(第二版)」(7ページ「3. 東北地整 奈曽川橋下部工工事」)
事例② 関東地整 横浜湘南道路トンネルその3工事
国土交通省関東地方整備局が管轄するトンネル工事の事例です。この工事では、シールドマシンによるトンネル掘削工事の立会確認で、タブレットPCやWeb会議システムを使用して遠隔臨場を実施しました。
特筆すべき点は、シールド坑内の通信環境を安定させるために、Wi-Fi環境の整備に注力したことです。また、リアルタイムで同時視聴できるシステムを採用することで、複数名による施工状況の把握や確認が可能になりました。
※出典:国土交通省「建設現場における遠隔臨場 取組事例集(第二版)」(13ページ「9. 関東地整 横浜湘南道路トンネルその3工事」)
まとめ
ICT活用が進む建設業界において、遠隔臨場の普及がさらに加速することが予想されます。先進的な事例を参考に、作業の精度や効率性を向上させる取り組みは、ぜひ積極的に取り入れていきましょう。
また、導入の際は、コストや機能、操作性、サポートやセキュリティ体制などを勘案し、各現場に適した機材やシステムを選定することが重要です。
現場作業員のタブレットのサポートなら「RemoteOperator Helpdesk」をご活用ください。
画面共有機能を利用すれば、現場作業員が利用しているタブレットでトラブルが起きたときに、情報システム担当者がリモートから直接状況を確認でき、トラブル解決へ導けます。
30日間の無料トライアルの利用も可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
